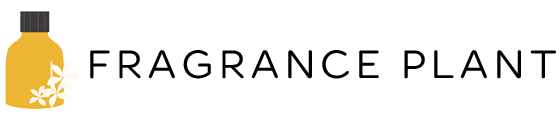映画「パフューム」を見た感想!18世紀フランスの香水文化が丁寧に再現されていて感激!!

映画『パフューム』は、2006年のドイツ・フランス・スペイン映画です。
舞台は18世紀フランス。
異常に鼻の利く主人公の一生を描いた作品ですが、当時の香水文化や香料植物、調香や蒸留のシーンなどが次々に出てきて、香水や香料が好きな方にとってはかなり興味深い映画だと思います。
しかし公開から20年近く経ってるんですね…
私は昔々に映画も原作本も見た覚えがあるんですけど、こまかい内容は忘れてしまっていて、また見たいなと思ってはいたんです。
今回全く関係ない目的でU-NEXTに再加入したら(いつも入ったり出たりを繰り返している)、この映画があったので見てみました。
終盤の方のネタバレはせず、主に香り関連のことに注目して感想を書いてみたいと思います。
十八世紀パリの街
不穏な音楽が鳴る中、物語の幕は開きます。
スポットライトは、牢屋に囚われている男の「鼻」へ。
彼は大勢の前で判決を言い渡されるんですが、「一体この男は何をしたんだろう?」というところから物語はスタートします。
そして映像は過去へ戻り、18世紀パリの街。
臭そうでしたね~~
当時のパリでもとりわけ悪臭がひどかった魚市場のシーンですが、とにかくビチャッ!!ドロッ!!ズルズルッ!!といった映像がひたすら続きます。
その流れで、魚売り場の台の下でポンッ!と生まれる赤ちゃん。
この映画のほとんどのシーンは忘れていたけど、この酷すぎる雑な出産シーンはなぜか覚えていたわ…
こうして生まれてきたのが、この物語の主人公「ジャン=バティスト・グルヌイユ」。
「グルヌイユ/grenouille」というのはフランス語で「カエル」のことらしいんですが、絶妙なネーミングですよね。
このグルヌイユは、生まれた瞬間から並外れた嗅覚を持っています。
そしてそのへんに落ちているものから草、木、石、水まであらゆるものを無心に嗅ぎまくり、その香りを言葉でどう表現したらいいのかと悩む日々。
まわりはそんな彼を気味悪がり、敬遠します。
考えてみれば、香りが自分にしか理解できないというのは孤独なものですね。
絵や音楽の才能であれば、描いたり歌ったりと表現する方法はなにかありそうですが、香りを言葉で伝えるのはなかなかむずかしく、かといってグルヌイユのような境遇ではそれを再現するための香料など手に入るわけもなく…
孤児として育てられた彼は、成長すると皮なめし職人へと売られます。
ここらへんまでは終始モワッとした暗い苔緑色みたいな画面で、見ている方もだんだん気が滅入ってくる…
しかしここでグルヌイユは、革を配達しにパリの街へ行くチャンスを手にします。
調香師の修行
パリの街でのグルヌイユの不審者ぶりといったら相当でしたね。
仕事ほったらかして香水店をじっと覗き込み、匂いに惹かれて少女を追いかけまわし、差し出された手を取ってむさぼるように嗅ぎまくる。
しかしこういうものはすべて、彼にとって生まれてはじめて出会う香りだったんですね。
こんなものがこの世にあるということすら考えてもみなかったでしょう。
パリで流行りの香水店(ペリシエという調香師の店)は、これまでのグルヌイユの世界にはないきらびやかな金色の世界で、華やかに着飾った男女が香水や化粧品を優雅に楽しんでいました。
こんなふうに見せられると、「香水」という存在のあり得ないぜいたくさを思い知らされます。
きれいなガラスの小瓶に入った、けっして自然には存在しない芳香のある液体。
グルヌイユは、ミラベル売りの少女(の匂い)に心(というか鼻)を奪われます。
ふつうの映画ならここで恋愛めいた”予感”くらいは挟んできそうなものですが、この映画にそういったものを期待してはいけません。
故意ではなかったものの、彼は少女の命をあっけなく奪ってしまいます。
そしてこの「香りが消えてしまった」出来事をきっかけに、「香りを永遠に保管したい」というどうしようもない欲望が芽生えてしまいます。
それにしてもこのグルヌイユ役の俳優さん、ものすごくハマり役ですね。
(英俳優ベン・ウィショー)
少女を目の前にしたときの驚異の眼差し、明らかにヤバすぎる挙動不審さ、香りを嗅ぐときの恍惚とした表情とか…
形のない「香り」を題材にした映画なので、それを伝える演技がどうしても必要なわけです。
そこを見事に表現している。
でもいま見てびっっっくりしたんですけど、ドイツ版Wikipediaによると、この役はディカプリオかオーランド・ブルームが検討されていたらしい。
それはまた、かなり話が変わってきそうな。。
バルディーニの香水ハウス
ケチなプライドと、でもどこかお人好しなイタリア人調香師ジュゼッペ・バルディーニ(ダスティン・ホフマン)、おもしろかったですね。
彼の店はパリに10数軒ある香水ハウスのうちの1つで、昔は流行っていたらしいですが今はさっぱり。
ライバルのペリシエさんの新作香水「愛と精霊」に嫉妬しながら、そのレシピをこっそりパクってやろうと何が配合されているか必死に嗅ぎ分けようとしていました。
それはまあいいんですが、その試香方法が興味深かった!
ムエットの代わりにハンカチを何枚も用意していましたけど、これって現実の世界でもそうだったのかな?
たしかに18世紀前半だとまだ紙は貴重だったでしょうし、スプレー瓶なんかもなかったですよね。
試香のやり方は、まず鼻をつまみ(なんで?)、香水をハンカチに1、2滴落とす。
そして素速く空中で縦に1振り、続いて横にふわ~っと流す。
そうやって空中に漂った香りを、クンクン嗅ぐ。
でも才能が涸れてしまったこの調香師にはハッキリとはわからないわけです。
ライムオイル、オレンジフラワー、シベットあたりまでは助手?に教えてもらってましたけど、あとはクローブだかシナモンだかで迷って迷ってイライラしてました。
あぁせつない…
そんなときにやって来たのが、天才的な鼻を持つ革の配達屋(グルヌイユ)。
グルヌイユは革を置きに地下の貯蔵庫に連れて行かれるんですが、そこで目にしたのはロウソクの灯りで照らされた壁一面の香料棚!!
グルヌイユも感動したでしょうが、私も感動!!感激!!香料が入ったいろんな形の瓶や壺!!
ジャスミン、イランイラン、レモングラス?、サンダルウッド?、シベット?
パッ、パッ、パッ、と画面が切り替わるので、もっともっとよく見せて~!!となりましたが、1つ1つちゃんと古びたラベルが貼ってあって、18世紀の香料貯蔵庫がリアルに再現されているんです。
ここらへんが適当だったら一気に冷めそうですが、この映画は地下室に限らず、香水店や調香台なども細部までしっかり作り込んであって、これだけでも一見の価値ありです。
香料以外にもカエルとか生物のホルマリン漬けみたいなのもありましたね。
グルヌイユは香料よりそっちを二度見してましたけど、一体何考えてるんでしょうね…嫌ですね…
グルヌイユの調香ショー
もちろんグルヌイユにとって香水の再現なんてお手の物なわけです。
まず「愛と精霊」に対して「ひどい香水!ローズマリー入れすぎ!!」からはじまり、バルディーニが知りたくてたまらなかったその成分(配合されている香料)を次々と言いはじめます。
といっても字も読めないし香料の名前なんて知らないので、鼻だけを頼りに香料瓶を集め、台の上に並べていきます。
彼によると、大流行の「愛と精霊」のレシピは、
ローズマリー(入れすぎ)、ベルガモット、パチュリ、オレンジフラワー、ライム、ムスク、クローブ(クローブだった!)、スチラックス(これが隠し味になっているっぽい)
ということでした。
ここからのグルヌイユの調香ショーは必見です。
ルールなんて完全無視したやり方で「愛と精霊」を再現してみせ、「僕ならもっと良い香りにできる!」と言い放ち、走り回って香料瓶を集め、天国のような香りへと変身させます。
…こうなるとバルディーニはもう抗えませんよね。
この調香師は、世間やライバルをギャフンと言わせる香りを何よりも望んでいたわけですから。
グルヌイユって、相手の望みを正確に嗅ぎ分けて自分の望むとおりに人を動かす(そして用が済んだ人には必ず不幸が起こる…)能力みたいなものが異常に長けてますけど、これも嗅覚によるものなんでしょうか。
どこまで狙ってなのかはわかりませんけど、そういうところも不気味です。
十三番目の香り
グルヌイユは調香師のために香水を作り、調香師はグルヌイユに香りの抽出方法を教える。
需要と供給は完全に一致し、”悪魔の契約”は見事に成立してしまいました。
「香りを”捕える”」というのがグルヌイユの真の目的ですよね。
彼にとってそれは生物から「香り」を取り出し、失われないように永遠に保存することを意味します。
それは表面的な意味では香料の抽出技術のことであり、この時代の調香師であればそのテクニックは当然身につけています。
バルディーニのもとで調香や蒸留について学ぶ一連のシーンは、見ていてとても楽しかったですね。
大量の赤いバラ(ガリカローズ?)が玄関からバサーーーッと投入され、それを使って水蒸気蒸留の実演をやってくれたのも良かった!
このアトリエでは、何気に重要なキーワードもたくさん出てきます。
あの「古代エジプトの香り」云々の話は、キフィとかそこらへんがモデルになってるんでしょうか。
「13種類の香料で完成する究極の香水」は、12種まではわかっているけど13種目がいまだにわからない、というものでした。
その伝説を蒸留器をバックに首を傾げながら聞くグルヌイユ。
これは今後の展開を暗示するようで、もう嫌な予感しかしない。
そんなある日、グルヌイユが求める香りは水蒸気蒸留では抽出できないということがわかります。
絶望のあまり、生命が危ぶまれるほどに弱るグルヌイユ。
しかし「グラースには”アンフルラージュ”という抽出方法があるらしい」ということをバルディーニから教えてもらったとたん、みるみるうちに回復します。
こういったエピソードからも、グルヌイユの生命はただ1つの目的のために存在しているということがわかりますね。
香水の「聖地」グラースへ
こうしてグルヌイユはグラース目指して旅立つんですが、この道中で見る南仏のグリーンがそれはもう美しいこと!
今まで暗い画面ばかりで、しかもこれからの暗い予感も手伝って、太陽に照らされたワイルドな風景がものすごく目に心地よかった!
あ~自然っていいな!と改めて思いました…
洞窟
この映画の中で、なんかこの洞窟のシーンだけは異質な感じがするんですよね。
それはここが「香りのない場所」だから??
グルヌイユは旅の途中でこの洞窟にたどり着き、この無臭の空間で生まれて初めて心からの安らぎを得ます。
これは凡人にはまったくわからない感覚ですが、生きている限りずっと何かしらの香りが語りかけてくるというのも疲れることなんでしょうね、きっと。
彼はこの安らかな場所から離れられなくなり、自分の計画も執着もすべて忘れてしまうほど長い時間を過ごします。
しかし周りに気を取られない環境に身を置くと、自然と意識は自分に向くわけです。
そこで気づいてしまうんですね、自分の身体は全く匂いがないってことに…
この衝撃的な発見によって彼の中で何かが変わり、グルヌイユはようやく洞窟を出てグラースへ再び旅立つことになります。
この映画って、香りと命(魂)を重ねて語る場面が度々あります。
「香り」というものには何かそういうものが含まれているような気がする、というのはきっと誰もが多かれ少なかれ感じていることでもありますよね。
この場面では、「香りのないグルヌイユ=”無”の存在」という描かれ方をしていました。
天国の2分間
ラベンダー畑の収穫シーンからはじまる天国のような2分間は、もう涙ぐんでしまうほどに美しかった…!!
見渡す限りに広がるラベンダー畑、収穫された花々、グラースの工場では鮮やかな黄色のジョンキルが山積みにされ、作業台ではズラリと並んだ女性たちがアンフルラージュをしている最中。
ジャスミン(かな?)のカゴや、乾燥させたラベンダーもあちこちに置かれ、荷車いっぱいのチュベローズも届きます。
でもね、そんな”良い香り”に浸れるシーンはたったの2分で終了するんですよ。
ちなみにIMDbに、「この時代はまだアンフルラージュ(冷浸法)は発明されていない」「映像に写っているのはラベンダーではなくラバンジン畑で、ラバンジンが発見されたのは20世紀になってから」と書いてありました。
なるほど、たしかに~
撮影時はラベンダーが満開じゃなかったので、色をデジタル処理したというのもどこかで見ました。
そりゃ実際はジョンキルもラベンダーもチュベローズも同時に満開!てわけにはいかないよね…
いや、でもそれでいいと思うんです。
だってこの2分間だけは、花で溢れかえった華やかなグラースを思いきり堪能したかった…!!
ここ以外のシーンは、基本的に全部暗いですからね。
全編147分のうち、どんな人にも手放しでおすすめできるシーンといったら、やっぱりこの2分間でしょう。
地獄のはじまり~怒涛のクライマックスへ
映画としてはここからが本番ですが、香料関連の注目ポイントとしてはこのへんでだいたい終了です。
というのも、ここから先はグルヌイユが別の次元に入っていくので。
彼は「手に入る香料を組み合わせて良い香りを創る」という通常の創作からは大きく逸脱して、その先へ向けてひたすら突き進んでいきます。
でもその次元のまま物語が終われば、まぁ想像の範囲内の映画になっていたと思うんです。
しかしこの映画は、そこから思いも寄らない方向へ二転三転していきますからね…
最後のシーンまで見終わったときは、もう一体何が起こったのか「ポッカーン…」です。
でも心の中には、確実に何かが残ります。
全編見終わった感想
まず、感情移入できる登場人物とかは1人も出てきませんよね。
それでも次々と何かが起こって展開も早く、役者さんの演技も素晴らしいので、まったく飽きることなく最後まであっという間でした。
おすすめポイント
何より、こんなに本気で「香水」や「香り」を描いた映画はほかにありません。
なにかの小道具とか演出のための”香り”ではなく、”香りそのもの”がこの映画のテーマです。
「香りとは何なのか?」「なぜ人は香りを求めるのか?」みたいな本質的なことを一貫して追求しています。
これほど無謀で最高で好奇心をそそるテーマがほかにあります??
こんな映画がもっと増えたらいいのに(できればもっと穏便なストーリーで)。
しかし…
物語は「究極の香水」に向けて一直線に進んでいくわけですが、なんにせよそれを「嗅いでみたい!!」とはあまり思えないんですよね。(思えないですよね?)
これが、幻の花!とか10万年前の樹脂!とかの香水だったらね。(でもそんなんじゃ健全すぎて面白くないか…)
「12の香料にあと1つ未知の香料を加えると、究極の香水が完成する」という設定は、かなりゾクゾクするものがあったし、うわぁ~何それ!嗅いでみたい!とも思いました。
でも13種類すべてが未知の香りとなると、もう想像もつきませんよ。
あ、調香師のところでグルヌイユが作った香水は、ぜひ嗅いでみたかったですね。
だいたいグルヌイユって植物の香りとかはあまり興味なさそうですよね?
いや子供の頃は興味持っていただろうから、もう”未知の香り”ではなくなったっていうだけのことでしょうけど…
でも調香師のところであれだけたくさん香料があったのに!
パチュリとかスチラックスとか、絶対あのとき初めて嗅いだでしょ?
グラースでも、あんな広大なラベンダー畑に目もくれず黙々と歩いてたし、ジョンキルもまったく興味なさそうにムッツリと脂に押し付けてたし!
まぁ彼にとって生きる理由はただ1つで、それ以外のことはすべて無意味だったんでしょうね。
それに「匂いは何でも知っている」という彼にとって、天然香料だけで作る香水はどんなに良い香りでも退屈だったのかもしれませんね。
じゃあ自然に存在しない合成香料がたくさんあって、まだまだ未知の香りを作り出す可能性も無限にある現代であれば、ちょっとは違ったんだろうか?
そういう問題ではないのかな。
香水セットが発売されていた!!
ここまで書いてから知ったんですが、なんと、このストーリー(原作)の各シーンを再現した香水セットがティエリー・ミュグレーから2006年に限定発売されていました!!!
香水は全部で15種類あるらしいんですが、この物語に出てくるのは当然”良い香り”ばかりではありません。
悪臭漂うパリの街、皮なめし職人、「愛と精霊」、それをグルヌイユが作り直したバージョン、洞窟、最後の方のあのシーンなど、想像もできなかった香りが実際に作られている…!!
すごい!かなりビックリ!!これは嗅いでみたい!!(でも今となってはかなり難しそう…)
香料会社IFFの協力で、この香水などの香りを同時に漂わせる上映会も行われたとか。
実際にそのシーンの香りを嗅ぎながらこの映画を鑑賞できるなんて、体験できた人が羨ましすぎます…!
↓香水セットの写真(リンク先はFragranticaページ)
15-piece perfume coffret by Thierry Mugler
まとめ
というわけで、映画『パフューム』を何年ぶりかに見直してみた感想でした。
今回は、記事を書こうと思ってできるだけ丁寧に見たということもありますが、昔この映画を見たときとはずいぶんと印象が違いました。
消えていく香りを、いつでも楽しめるように所有したい!というのは、いつの時代も変わらない普遍的な欲求です。
それに香りというものの神秘は底なしで、「まだだれも嗅いだことのない香り」という誘惑とスリルは、たしかに人を狂わせるものがあると思います。
こういう”不気味さ”とか”よくわからなさ”は、「香水」という芸術ならではのものかもしれません。
たぶん見る人を選ぶ映画ですが、「香り」に惹かれる方ならきっとなにか感じるものがあると思うので、気になる方はぜひ見てみてください!